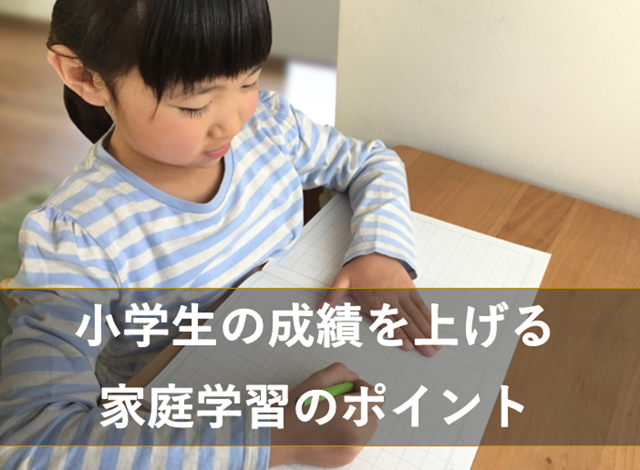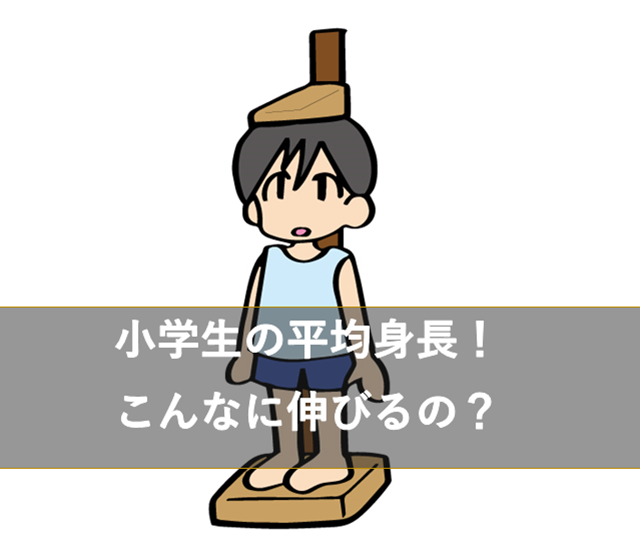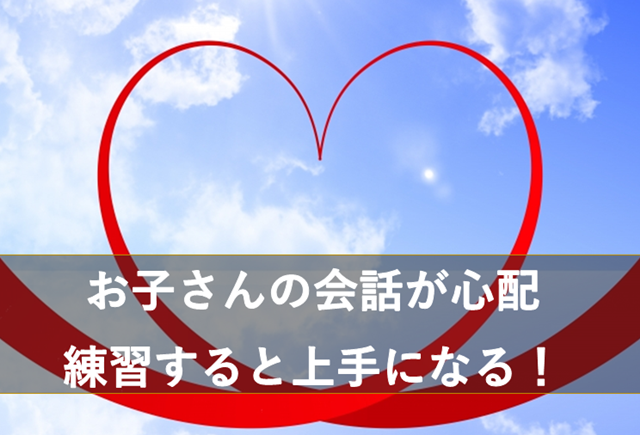
お子さんが友達とおしゃべりしているとき、話し方が一方的だったり、会話が成立していないときってありますよね。
自分が話したいことだけ話していたり、相手が話しかけているのに自分の話を優先させたり。
そんな場面を見かけると、親として、「友達と上手くやっていけるのだろうか?」と不安になってしまいます。
わが家の長男は、友達との会話がうまくできていないと学校から言われたことがあります。さらに発達検査を受けるように言われました。
子供の会話ができないことを、発達障害のせいにしようと考えたのかもしれません。
でも、この会話の未熟さは誰にでもあることなのです。だって子供ですから。会話に限らず、上手くできないことはたくさんあるのです。
できない時にはどうするのか?
それは練習あるのみです。苦手な会話は、実は経験不足や練習不足の場合が多いです。
そして、多くの場合、上手くいかない会話は、練習していくことによって、上手になっていきます。
日常生活での会話の練習、友達との関係をスムーズにしていく練習を、ソーシャルスキルトレーニングと言います。
ソーシャルスキルトレーニングは、学校や療育機関でも広く実践されています。ご家庭でも簡単にできるものが多く、とてもお子さんの発達に有効です。
「うちの子大丈夫かな?」と心配に感じたら、ぜひソーシャルスキルトレーニングを親子でやりましょう。お子さんの成長を間近で感じることができます。
会話の練習は、電話ごっこで上手になります
小学生の子供の会話で大切なのは、相手が話しているときには自分は聞く、相手が話し終わったら自分が話すという、言葉のキャッチボールをすることです。
相手の話を全く聞こうとしていなかったり、自分の話したいことばかり話したりする場合は、この言葉のキャッチボールが上手くいっていません。
会話のマナーやルールは、電話ごっこで身につきます。電話では、基本的に話す側と聞く側に分かれます。同時にしゃべっても、お互いに意味が分からないからです。電話という道具があることで、お子さんは聞くことにも集中するようになります。
幼い子の遊びのように感じるかもしれませんが、小学生のお子さんには効果的です。遊びの中で身につけるものは、実は多くあるのです。
高学年の場合は、「電話ごっこ」などはしようとしません。名前を「コミュニケーショントレーニング」などに変えて話しましょう。
電話ごっこの効果
電話ごっこで、次のような効果が期待されます。
・「話す」・「聞く」の切り替えができるようになる
・言葉のキャッチボールが自然に身につく
特に会話のきっかけは、日常生活の中ではなかなか練習しません。なんとなく身につけていくものだからです。
「ねえ」「ちょっと」など、大人は様々な会話のきっかけになる言葉があることを知っています。でも子供は意外と知りません。突然相手に話しかけたり、聞いていない相手に話していたりします。話すきっかけやタイミングは、会話するときの大切なポイントなのです。
電話ごっこの方法
電話ごっこでの会話練習の仕方を説明します。
・電話2台(段ボール等で作ったものやおもちゃでもOK)
①1人1台の電話もしくはスマホを持つ。
②向かい合って座る。
③親の「もしもし」から始める。
④今日学校であったことを会話で聞く。
⑤5分程度で終了する。
⑥お子さんの会話の仕方で良かったところを伝えてほめる。
ほめるポイントは、会話のタイミングや受け答えの仕方についての成長です。相手の話を聞き終えてから自分の話をした場合や、「ねえ」「ちょっと」など、会話のきっかけとなる言葉を上手に使えたところなどです。お子さんとおしゃべりしながら、ほめるところを探しておきましょう。
ほめることで、お子さんの会話の仕方は格段に上達していきます。教え込んだり叱ったりするよりも、効果的なのがほめることです。もちろん、良かったと本人も自覚できるような内容でないと、ほめる効果はありません。
始める前に、「今日は、あのねという言葉をつかってね。」など、目標を持たせておくとほめやすくなります。
会話が成り立たない原因は経験不足
電話ごっこで会話がスムーズにできるようになります。そもそも、お子さんのお会話が成立しない原因や心配する理由は何なのでしょうか。
実は、お子さんの会話がぎこちなかったり、そばで見ていて心配になったりする原因は「会話の経験不足」です。
子供はいろいろなことを、成功と失敗をしながら学んでいきます。お友達と遊びたいときに、「いっしょに遊ぼう。」と声をかけて遊べた場合、この言葉かけは成功したことになります。
でも、無視されたり断られたりした場合は失敗したことになります。失敗した場合、どうすればいっしょに遊べるか考えます。
何とか言葉を変えながら遊びたいということを伝えるかもしれません。友達が遊びたくなるような気を引く行動をするかもしれません。失敗してもどうにかして遊ぼうと努力すること。これがお子さんの経験になり、学びになります。
現在の子育てでは、お子さんの失敗を先回りして防ごうとしますので、そんな経験をする機会は昔に比べて極端に少なくなっています。ですから、会話を心配するといったことが出てくるのです。
経験不足が原因ですから、しっかりと経験させていけば、上手に会話ができるようになります。発達検査を受けたり、心配をしたりするのは、経験しても学んでも、何度繰り返しても上手くいかないときでいいのです。
まずは、「電話ごっこ」で、お子さんの会話の力を高めていきましょう。
ソーシャルスキルトレーニングでお子さんの生活は変わる
会話ごっこのように、日常生活で必要な技術の練習をソーシャルスキルトレーニングといい、省略してSSTと書きます。
ソーシャルスキルトレーニングには、生きていく上で必要な技術ですから様々なものがあります。箸の持ち方から挨拶の仕方、話の聞き方から上手な話し方、友達との距離のとり方から手のつなぎ方、お願いの仕方から断り方など、例を挙げればきりがありません。
もし、お子さんの様子を見ていて、「ここが不安だな」「心配だな」と感じるところがあれば、そのことのソーシャルスキルトレーニングを行うことで不安はなくなります。
親が不安に思うことは、実は子供は困っているという場合は多いです。ですから、積極的にソーシャルスキルトレーニングをすることをおすすめします。
ソーシャルスキルトレーニングは、専門の本も多く出ていますが、自分で工夫して考えることもできます。
ソーシャルスキルトレーニングの簡単な方法はこうです。
②解決の方法を親が考える
③困っている場面をイメージして、練習する
④身につくまで継続して練習する
トレーニングですから、③が一番重要になります。会話で困っているのであれば会話の練習、空気が読めないのであれば状況を理解する練習など。
1日のトレーニングは数分間にします。お子さんの負担にならない短時間にすることが、親の負担も減らします。数週間、数か月で身につくことをイメージして、毎日少しづつトレーニングを続けることが大切です。
今回は、会話がスムーズに進まないお子さんの例を考えました。他にもたくさんあります。特に親が心配するのは、友達との関わり方です。
自分の気持ちが上手に伝えられず、友達とトラブルになることって多いのです。
そして、小学生のお子さんにとっては、勉強の悩みよりも友達とのトラブルのほうが緊急度も重要度も上です。
特にこの傾向は、高学年になるにつれて強くなりますので、低学年のうちに親が気づいたことは、早めにソーシャルスキルトレーニングで練習し、解決しておくことをおすすめします。
家で親子でできるソーシャルスキルトレーニングの本はたくさん出版されています。ご自分でできそうなものを選んでやってみましょう。まずはチャレンジです。