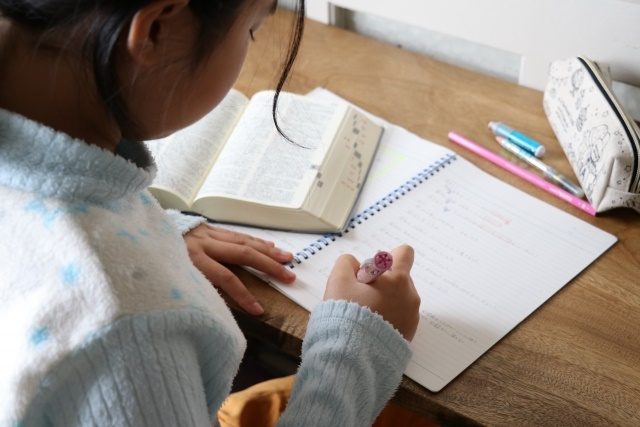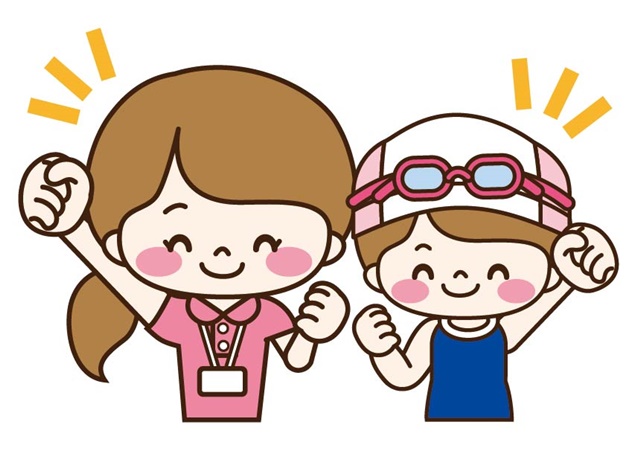小学校の運動会で、カメラやビデオ片手に子どもたちの撮影をして回る保護者は多いです。わたしもその一人です。せっかくの機会なので、子どものがんばる姿を写真に収めたいと思います。でも、何も考えないで写真を撮っていると、何だかどうでもいいような写真ばかりが撮れています。
今回は、運動会でお勧めのシャッターポイントについて、数々の失敗から学んだ極意を伝授致しましょう。(たいしたことなくてすみません)
カメラとビデオ、どちらがいい?
わたしはよく悩んでいました。カメラとビデオ、どちらを持っていこうか。結局二つとも持っていったりして、どちらも中途半端になったりしました。
結論から言うと、どちらでもいいと思います。好きな方でいいと思います。音声なしで、その場面その場面を楽しみたいならばカメラ。動きも音声も楽しみたいならばビデオがいいでしょう。
うちではビデオ係が奥さん、カメラ係がわたしとなっています。複数で運動会に行く場合は、役割分担するといいかなと思います。
わたし個人のおすすめは、カメラです。瞬間が撮れますし、最近のデジカメは、動画もしっかりと音声付きで撮れます。できれば安いものでもいいので、一眼レフのデジカメがお勧めです。
カシャカシャカシャと、一回のボタン操作で、3~4枚の写真が瞬間的に撮れます。走っている場面だと、宙に浮いている瞬間まで撮れます。何だかカッコいいですよ。
でもまあ、カメラでもビデオでも、どちらでも好きな方で撮影するといいと思います。どちらか一つに絞らないと、子どもの応援をせずに撮影だけ頑張ったということになりかねませんので、注意が必要です。
入場・開会式の撮影ポイント

運動会の始まりは入場行進という小学校も多いはずです。この入場行進は、まだ会場に来ていない家族も多いため、撮影ポイントはたくさんあります。子どもも疲れていませんので、元気な笑顔を撮ることができます。
入場行進前の子どもたちが並んでいる場面から撮りましょう。まだ始まっていないので、子どもに「こっちを見てごらん。」と声をかけることも可能です。すでに保護者が近づけないようにされているところはあきらめましょう。
入場行進中は、どこからでもかまいません。動き回るよりも、一カ所に決めて行進してくる様子を撮りましょう。真横に来た場合は、もうシャッターチャンスとしては遅いですので、近づいてくるときから真横に来るところまでがシャッターチャンスです。
開会式では、あまり撮影するものはありません。並んでいるところ、全体的な様子などを撮影しておくといいでしょう。子どもは、友達が映っていると「あっ、〇〇ちゃんだ!」と喜びます。子どもがいる付近の周りの子も撮っておきましょう。不要な場合は削除するだけです。
開会式中は、子どもたちに近づけないので、遠くから子どもの姿を1~2枚撮っておくといいと思います。望遠機能やズーム機能がついているカメラが便利です。一眼レフカメラなら、レンズを望遠に交換してもいいです。かなりよく撮れます。
かけっこ、徒走の撮影ポイント
かけっこや徒走でお勧めの撮影ポイントです。まずは子どもたちが並んでいるところを撮ることをお勧めします。入場門にいると思います。保護者の入場は制限してある場合が多いので、できる範囲で近づきて撮りましょう。
走る場面では、3つの撮影ポイントが考えられます。スタート、走っている場面、ゴールの瞬間です。お勧めは走っている場面です。スタートは動きがあまりありませんし、ゴールは周りの人が入り込みます。
特にコーナー付近での撮影がお勧めです。カメラの連射機能、動体モードなどを使って、瞬間が撮れるようにしておきましょう。子どもがコーナーに入ったら、数枚撮影します。いくつか前の組で練習しておくと安心です。
ここで一眼レフの力が発揮されます。動いている子どもの姿をはっきりと捉えてくれます。ピンボケやブレていたなんてことになりません。わたしはカメラを替えて走っている場面を撮ったとき感動しました。
玉入れ、綱引きの撮影ポイント
玉入れや綱引きなどの大勢の競技が運動会にはあります。ここでは、入場前の様子を撮りましょう。その後場所移動し、入場の様子や玉入れの様子を撮影しましょう。
これらの大勢の競技は、学校や学年によって内容が異なってきますので、玉入れを例に説明します。
【玉入れの場合】
撮影のポイントは3つ考えられます。玉入れの準備、玉入れの競技中、そして玉入れ終了後です。
準備では、構えていポーズを撮りましょう。やはり望遠機能があったほうが便利です。アップで撮ることができます。周りの子も2~3人含むように撮りましょう。
競技中は、どこにいるか分からなくなる場合もあります。子どもを探して撮りましょう。無理な場合は、全体的に数枚撮っておきましょう。
ダンス、組体操などの表現運動の撮影ポイント

最近の運動会のメインは、かけっこよりもダンスや組体操のようです。盛り上がり方が違います。ここでも子どもとの距離が遠いと、あまり上手く撮影できません。近づけない場合は、望遠やズームを使いましょう。
ダンスも組体操も、どちらを向いて演技するのかが重要です。せっかく近くの場所で撮影できても、後ろ姿ばかりでは残念です。ほとんどの演技が本部テントを正面にして行われます。ご来賓の方々がいらっしゃるからです。
ですから、一番いい撮影ポイントは、本部テント付近です。できるだけ前の方で撮影しましょう。しかし、立ち入り禁止のテープを越えるなど、ルール違反はいけません。
子どもがどの辺りで踊るのか、事前に子どもに聞いておく必要があります。人数が多い学校になると、同じ服装の子から自分の子どもを探すのは一苦労です。
カメラの場合でも、数枚撮影した後、ビデオモードや動画モードに変えて撮影することをお勧めします。小さなデジカメでも、音声まで録音してくれるので、踊っている様子を録画できます。
閉会式・終了後の撮影ポイント
閉会式では、二つのシャッターチャンスがあります。一つは入場行進です。やや疲れ気味の様子を撮影しておきましょう。入場行進が無い場合も多いようです。その場合は、子どもの様子を数枚撮っておくとよいでしょう。
もう一つが、万歳や拍手など、子どもがアクションをとったときです。「白組の勝利です。」などのアナウンスの後に万歳や拍手があります。その様子を撮っておきましょう。
その他の撮影ポイント
競技以外の撮影ポイントです。せっかく子どもと一緒に学校にいるのですから、たくさん写真を撮っておきましょう。
まずはテントです。子どもが待機している場所です。学校によっては保護者の立ち入りは禁止です。可能な場合は、子どもに声をかけて、座っているところを友達と一緒に撮りましょう。
お昼の時間は、子どもが一番楽しみな時間です。自然と笑顔も多くなります。ここでは、思いっきり近づいて撮影できますので、お弁当を食べている様子や家族と一緒のところを何枚か撮っておきましょう。
撮影後の楽しみ方
撮影後の楽しみ方です。思いっきりわが家の楽しみ方ですみません。大事にしていることは、「その日の行事はその日のうちに!」です。
2~3日経つと、運動会の写真を見せても、盛り上がりはいまいちです。その日のうちにパソコンやテレビにつないで、鑑賞会をしましょう。
テレビなどの大画面がお勧めです。DVDやブルーレイにまとめておくのもいいと思います。とにかく、その日のうちに見るようにしています。DVDは後日です。
うちでは、夕食時に写真を見て、寝る前に寝室でビデオをみています。ビデオはプロジェクター機能がついているものを使っているので、部屋を暗くして天井に映します。みんなで横になって見れるのでお勧めです。
長くなってしまいましたが、小学校の運動会での撮影ポイントについてでした。
いい写真が撮れることを願っています。
運動会のおすすめ情報をまとめました。よろしければご覧ください。