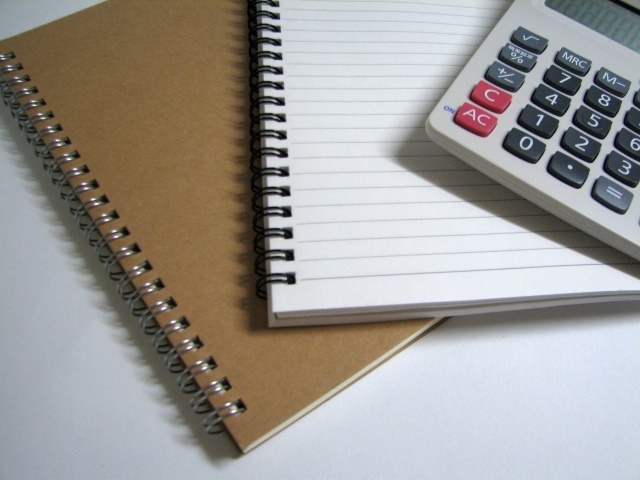
日商簿記3級試験に独学で勉強し、資格の取得を目指す企画「ぼきプロ」の勉強報告です。
週に1回報告することに決めました。このペースでいくと、11月の日照簿記3級の試験まで、およそ20回の報告をすることになります。
「簿記って何?」という素人レベルのわたしが、日商簿記3級に合格するまでにやったことを記録していきますので、これから日商簿記3級の資格を目指す方の参考にしていただけるとうれしいです。
しかし、当然まだ合格はしていませんし、合格するかも不明です。その点はご了承いただき、あたたかい目で見ていただけるとありがたいです。
では、「ぼきプロ」2回目の独学勉強報告です。
ぼきプロ2回目の勉強状況
日商簿記3級試験の合格のための勉強は、前回決めた勉強計画に従って進めています。まだあまり進んでいません。
①簿記ってどんなものなのか、全体を勉強する。 ☜ 今ココです!
↓
②教科書でしっかりと勉強する。
↓
③問題を解きながら勉強したことを確認する。
↓
④過去問で実力を試す。
↓
⑤忘れないように問題にチャレンジする。
↓
試験を受ける! → 合格するまで続ける!
現在は、①の「簿記ってどんなものなのか、全体を勉強する。」段階です。
簿記の説明が書いてあるマンガを読んで、簿記について大まかな知識を学んでいる最中です。ページ数でいくと、現在ちょうど三分の一くらい読み終わりました。(遅い!)
こうやって勉強の進み具合をレポートしていくと分かるのですが、勉強の進み具合は遅いです。理由は、やはり簿記素人なので、言葉の壁が厚いです。
マンガ中心とはいえ、初めて聞く難解な言葉が、次から次へと出てきます。ですから、一度に多く読み進めると、かなりの苦痛です。一瞬で意味が分からなくなります。
でも、最初の教材でマンガを選んだのは正解でした。
難解な言葉だらけですが、マンガのイラストがあるおかげで、実際の場面をイメージできます。こんな場面で、こんなふうに使うんだということが分かります。
でも、もう少しスピードアップしなければいけないなと思いました。反省です。
学んだこと
今回学んだことは、仕訳(しわけ)のルールです。
・仕訳とは、物を売ったり買ったりする取引の発生後に行われる簿記の最初の作業です。
・この仕訳では、様々な項目の記入に勘定科目が用いられます。
大きくいうと、この二つです。
勘定科目について、いくつかの解説が載っていて、いろいろな勘定科目の記述の仕方について学びました。
詳しい学習内容については省きますが、勘定科目の種類は多く、名称も難しかったのが正直な感想です。
今回は、マンガで読み流したのですが、これを覚えるとなると大変そうです。
勘定科目の学習をしていて、初めて銀行の当座預金というものが分かりました。
難しかったこと
読んでいると、「あ~、なるほどね!」と分かるのですが、勘定科目の多さにびっくりです。
会計事務をされている方々にとっては、馴染みの言葉なのかもしれませんが、どれも覚えにくいものばかりでした。
思わず「大丈夫かな~?」と自分のことが心配になりました。
特に難しかった勘定科目は、売掛金と買掛金、引当金、減価償却の直接法と間接法です。マンガ部分の説明があったので、少しイメージできましたが、説明できるかというと「?」です。
次の目標
次の学習は、後半部分を読むことです。できれば全部読みたいと思います。そうしないと、このペースでは間に合わないかもしれません。
後半部分は、実際の帳簿記入の勉強のようです。何だか実践という感じがします。
まだスタートしたばかりなのですが、ちょっぴり焦りもあります。まだ学習の全体が見渡せていないからだと思います。
毎日少しずつでも勉強を進めていきます。目標は1日30分。短すぎ?


