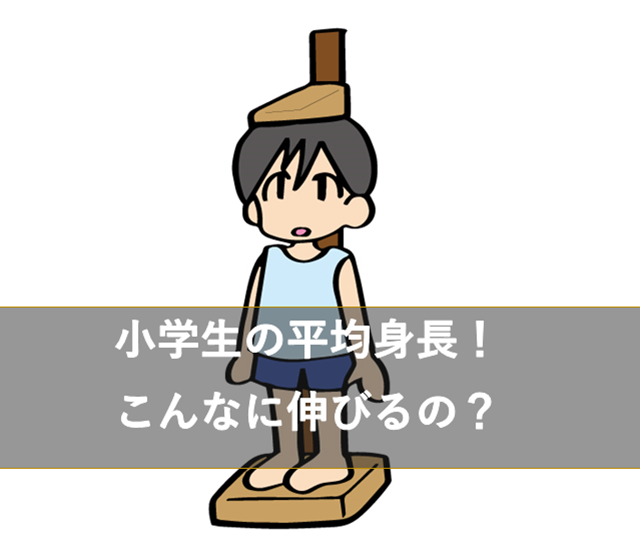小学校の勉強で、「得意」「不得意」がはっきりと分かれるのは算数です。国語は嫌いと答えるお子さんが多いのに対して、算数は苦手なお子さんが多いです。
算数が苦手なのは、勉強したことが理解できていないまま、次の勉強に進んでいることが原因です。
小学校3年生の「わり算」の勉強で説明します。
式は6÷3で、答えは2個です。わり算の計算には、かけ算九九を使います。もし、かけ算九九を覚えていない場合は、割り算はできるでしょうか?
残念ながらできません。どれだけわり算の計算を教えても、かけ算ができていないと計算できないのです。ちなみにかけ算九九は2年生で勉強します。
つまり、2年生の勉強をしっかりと身につけていないと、3年生の勉強ができなくなってしまいます。ここが算数の難しさです。
では、どうすれば3年生のわり算ができるようになるのでしょうか?
一番の近道は、2年生の九九に戻って勉強し、九九がしっかりと言えるようになることです。そうすれば3年生のわり算の計算ができるようになります。
算数が苦手なお子さんが、苦手を克服する方法は「戻る」ということです。
しかし、多くの小学生が自分のつまずきに戻りません。その理由も単純で、自分がどこでつまずき、分からなくなっているのかが分からないからです。
大人の目から見ると、かけ算でつまづいているなと分かっても、子供には自分がつまずいているところは分かりません。それは子供には難しいことです。ですから、お子さんんが算数が苦手な場合、どこでつまずいているのかを大人が気づいてあげることが大切です。
お子さんは、自分がつまずいているところができるようになると、次々と問題が解けるようになっていきます。算数は答えがはっきりしていて学びやすい勉強です。苦手のままにしておくなんてもったいない。つまずきに戻って勉強し、苦手を克服していきましょう。
「算数が苦手」は小学校の高学年に多い
算数が苦手と答える小学生は、高学年になるほど増えていきます。その理由は、先ほど3年生のわり算でご説明した通りです。どこかの学年でつまずいてしまうからです。
少し付け加えて説明すると、1年生で勉強したことを使って2年生で勉強し、2年生で勉強したことを使って3年生で勉強し、3年生で勉強したことを使って4年生で勉強します。このように算数の勉強はつながっているのです。「算数は積み上げの勉強」と言われています。
ですから、どこかの学年で分からないことが一つできると、その先が分からなくなってしまいます。
小学5年生で体積の勉強をします。体積の勉強が分かるようになるためには、4年生までに勉強した次のようなことが分からなければいけません。
・長方形や正方形の面積
・広さ
・かさ
・かけ算九九
体積を求める公式自体は「たて×よこ×高さ」と簡単なのですが、前の学年で勉強したいろいろなことが分からないといけないのです。
小学6年生で勉強する分数のわり算になると、もっと多くのことを理解しておくことが必要です。
・公倍数、公約数(6年生)
・倍数、約数(6年生)
・分数のかけ算(5年生)
・分数の表し方(3年生)
・わり算(3年生)
・かけ算九九(2年生)
7つありますが、細かく調べるともっとあります。
分数のわり算の勉強が分かるようになるためには、それまでに勉強した多くのことを分かっておく必要があるのです。どれか一つ抜けていると、分からなくなってしまう場合があります。
高学年の算数では、低学年の頃から勉強していることを使って問題を解いていきます。ですから、高学年になるにしたがって、算数が苦手なお子さんが増えてくるのです。
つまずきには「戻る」ことが克服の第一歩
算数が苦手な原因が分かれば、克服することはできます。お子さんが分かっていないところ、つまり「つまずいているところ」に戻って勉強をするのです。
何年も前に勉強したところに戻って、もう一度勉強するって、何だか面倒ですし、遠回りをしているような気持になります。
でも、つまずいているところに戻って勉強することが、一番の近道なのです。お子さんは、ちょっとしたことでつまずいている場合が多く、そのつまずきが解決するとスラスラと問題が解けることが多いです。
問題は、お子さんがどこでつまずいているのかということです。
その地点に戻って勉強をすればいいのですが、どこでつまずいているのかは、お子さんには分かりません。つまり、どこを勉強すればいいのかも分かりません。
算数が苦手なお子さんに、「ちゃんと勉強しなさい!」の言葉は酷かもしれません。お子さんがつまずいているところを誰かが気づいてあげる必要があります。つまずいているところが分かれば、克服はすぐそばです。
つまずき発見の方法
つまずき発見の方法はいくつかあります。
・まとめテスト、チェックテストをする
・毎回のテストで確認する
・ふだんの勉強の様子を見ておく
一番早いのは、勉強の専門家である先生に聞くことです。小学校の先生、塾の先生、家庭教師の先生など、お子さんの勉強の様子をよく見ているので、聞けば教えてくれます。
ご家庭でもできるのは、テストのチェックと勉強の様子をみておくことです。
テストで間違えたところは、よく理解できていない場合が多いです。テストは点数ばかりみるのではなく、どこを間違えているのかをチェックしておきましょう。
毎日の宿題もチェックしやすいです。お子さんが教えてと聞いてきたところや間違えているところは、よく分かっていないつまづきの部分です。
テストの場合も、宿題の場合も、分かっていないところを発見した場合は、前の学年の勉強に戻ります。
使うのは、前の学年の教科書です。なぜ教科書を使うのかというと、お子さんの記憶には、授業で教えてもらった記憶が残っているからです。場合によっては、前の学年の教科書を読んだだけで思い出すこともあります。
前の学年の教科書がない場合は、購入するか参考書を使うか、または親が教える方法があります。
塾や家庭教師の先生がいる場合は、お子さんが質問すればいいでしょう。しっかりと教えてくれます。
ご家族が教える場合は、次のように教えていくとよいでしょう。いくつか例を紹介します。ご自分でアレンジしてくださいね。
つまずきへ戻る算数の勉強の例
ご家庭でできる勉強方法の例です。いくつかの例を紹介します。
小学3年生のわり算でのつまずき
小学校3年生のわり算では、あまりの計算も出てくるので、つまずきやすいポイントです。わり算の勉強が分かるためには、次のことが大切です。
どれか理解できていないところがあれば、復習させるようにしましょう。一緒に考えたり、教えてあげるのもOKです。
・式の立て方(3年生)
・わり算の計算の仕方(3年生)
小学4年生のわり算のひっ算でのつまずき
ずっと使うわり算のひっ算の勉強です。正しいやり方を覚えていないと、5・6年生、そして中学校の数学でも苦労することになります。
わり算のひっ算の勉強が分かるためには、次のことを復習させましょう。
・式の立て方(3年生)
・わり算の計算の仕方(3年生)
・筆算の仕方(4年生)
小学5年生の三角形の角の大きさでのつまずき
角の大きさは、苦手なお子さんにとっては意味が全く分からないところです。特に図形の勉強は、少しずつ学年ごとに積み上げられています。
全部の学年が関係するので、どこで分からなくなっているのか分かりにくいです。いくつか復習のポイントがありますので、どこでつまずいているのかチェックしましょう。
・直角と三角形(2年生)
・二等辺三角形、正三角形(3年生)
・角の大きさ(4年生)
・図形の角(5年生)
算数が苦手なお子さんは、今までの勉強のどこかでつまずきがあります。丁寧につまずいている部分の勉強をすることで、苦手は克服できます。