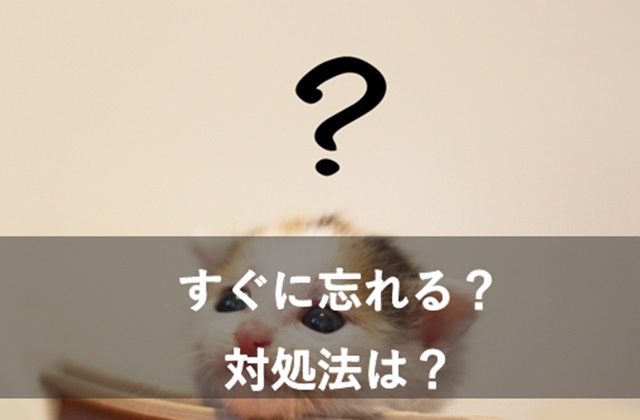子供が小学生になると、宿題などで教科書の音読を聞くことがあります。子供の頃、よく国語の教科書を宿題で読みましたよね。
子供が上手に文章が読めていないと、「えっ、うちの子大丈夫なの?」「学校の勉強についていけてないのでは?」と心配になります。
今回は、文章をスラスラと読めない場合の練習の仕方についてまとめます。
6歳で文字がスラスラ読めないのは当然
6歳といえば、小学校1年生くらいの年齢です。この段階でスラスラ読めないのは、実は当たり前です。なぜなら、ひらがなをはじめとした文字は1年生の1学期に勉強するからです。
小学1年生の1学期に、「あ」「い」「う」など、1文字1文字の読み方・書き方を勉強します。
子供にとっては、このレベルです。それなのに、いきなり多くの文字がならんでいる文章を、スラスラ読めるはずがありません。大丈夫です。6歳でスラスラ読めないのは当然のことなのです。
例えば国語でローマ字を勉強します。Aを「あ」と読みますよね。
「tanosiikotoga arimasita」→「たのしいことがありました」
勉強したからといって、アルファベットの文章をスラスラ読めるでしょうか?
無理です。
大人でもそうです。中国語や韓国語などの自分が知らない文字を勉強したとします。勉強したからといってスラスラ読めますか?
おそらく難しいのではないでしょうか。
ですから、6歳でスラスラ読めなくても心配はいりません。
もし、周りにスラスラ読める子がいたとしても、気にする必要はありません。その子は、少しだけ勉強が進んでいるのです。すぐに追いついていきます。
スラスラ読めないのは発達障害(学習障害)なの?
発達障害のお子さんの中には、文字が話している言葉と一致せずに読みづらい子もいます。
1年生の勉強をしていく中で、文字がまったくわからない、覚えられない、書けない場合は発達障害の可能性はあります。
その場合は、お子さんに合った手立てで勉強していけば、徐々に文字に興味を持ち、読み書きができるようになると思います。
今回は“スラスラ”ということを考えています。つまり、文字は読めているけれども、スラスラ読めない場合です。これは単に読む練習が不足している場合が多いです。
しっかりと読む練習をしていくことで、スラスラと読めるようになっていくと思います。
発達障害は一人一人違います。学習障害があっても無くても、お子さんの特性を考えて練習していくことが大切です。
これから紹介する方法が難しい場合は、こちらもお試しください。
➤ビジョントレーニングで読む練習
1年生の拾い読みがスラスラ読めるようになるには?
説明したように1年生で文字の勉強をします。勉強したてでスラスラ読めないのは当然のことです。
一字一字をたどたどしく読むことを、『拾い読み(ひろいよみ)』と言います。文字を勉強はじめた時期は、みんなどの子も拾い読み状態です。
では、どうすればスラスラ読めるようになるのでしょうか?
スラスラ読めるようになるには「読む練習」をします。
何だか当たりまえのことですよね。でも、これが一番効果があります。1年生の場合、文章を読む練習は一つです。
後追い読みです。
親が読んだ後、子供が同じところを読みます。シンプルな読み方の練習方法です。
①国語の教科書をひらく
②読むところを決める
③親は子供のななめ後ろか横にすわる
④親が1文読む
⑤子供が同じところを声に出して読む
⑥次の文を同じように読んでいく
気をつけてほしいのは声の大きさです。最初は声が小さいです。「もっと元気よく!」など言わなくても大丈夫です。読めるようになれば、自然と元気よく読めます。
文字がスラスラ読めるようになるコツは、文字を目で追わせながら後追い読みをさせることです。これをしないと意味がありません。
ですから、最初のほうは文字を指で押さえさせながら読むのもいいと思います。
同じところを読む練習を1日2日…と続けていくと、子供は文章を暗記してきます。その場合、教科書の次の文章に進むといいでしょう。
上手に読めるようになったことを、しっかりと褒めてあげてください。
文字がスラスラ読めるようになる方法
小学生のお子さんは、どの学年の場合も1年生と同じ練習方法で大丈夫と思います。もう少し付け加えた練習方法も紹介しておきます。
実際に小学校で行われている場合も多いです。家庭でする場合は、お子さんと1対1でできるので更に効果的だと思います。
①国語の教科書など、読むところを決める
②1日1回、後追い読みで練習する
(読んでいるところは目や指で追わせる)
③時々、1文ずつこうたいで読む
(「。」でこうたいする)
④ある程度覚えてきた段階で子供だけで読む練習をする
(親は必ず聞く)
⑤スラスラ読めるようになるまで、毎日続ける
⑥次のお話に進む
子供の読む練習なのですが、意外と親が大変です。根気よく、3か月間は続けるつもりでがんばってください。時間は5分以内がいいです。子供も親も無理しません。
基本的には①と②を毎日繰り返していきます。
3日に1回くらい①③の順でやってみましょう。「。」で交代しながら読んだりすると、ゲーム的な面白さもあって子供は喜びます。(丸読みと言います)
教科書の同じところを繰り返し読んでいると、1週間~2週間くらいで、子供が目に見えて上手に読めるようになってきます。この段階で①④の順で練習していきます。
・最初は親の後を読む
・慣れてきたら「。」で交代しながら読む。
・上手になってきた段階で一人で読ませる
大切なポイントは続けることです。数日がんばったくらいでは、スラスラ読めるようにはなりません。
毎日短時間でも、続けることによって読むことが上手になっていきます。
最低でも1か月間は一緒に頑張ってみてください。
「読めるようになった!」という経験を繰り返していくと、お子さんは読むことに自信をもつようになっていきますよ。
小学生の音読Q&A
小学生の音読について、よくある質問にお答えいたします。
読み間違いはどうすればいいのか?
特に初めて読むところや、まだ数回しか読んでいない文章等になると、子供は読み間違いをします。
文字を抜かしたり、違う言葉で読んだり、1行先を読んだり…。
どうすればいいのか?
そこで止めて言い直させるべきか、そのまま気にせず音読を続けるべきか迷いますよね。
読み間違いは気にせず、どんどん音読をするようにしましょう。
せっかく頑張って読んでいるのに、途中で止めるなんてもったいない。
まずは「音読できた!」という子供の達成感を大事にします。気にせず続けて、しっかりとほめるようにしてください。
ですが、そのままにもできません。
次に読むときに、「ここを飛ばさず読んでね」「この漢字は○○と読みます」などのアドバイスをします。
一度にたくさんのアドバイスはNGです。1~2つくらいにしておきましょう。少しずつ上手に音読できるようになっていけばいいのですから。
これを繰り返していけば、次第に上手に読めるようになっていきます。
子供といっしょに音読を楽しみましょう。