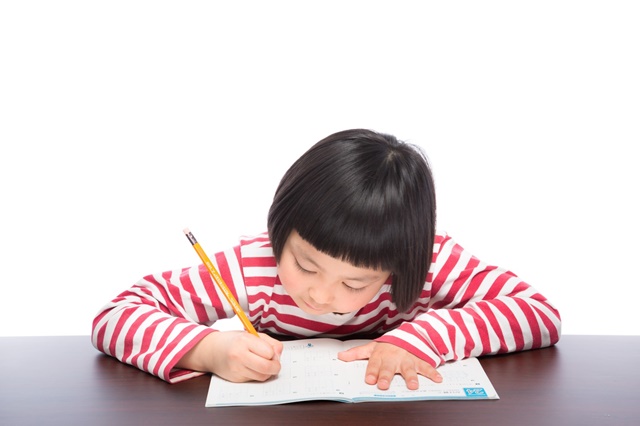
小学生、中学生の勉強でよく言われます。「勉強では、やり直しが大切!」という言葉です。
やり直しが大切ということは、分かるのですが、実際に完璧にやり直しをしている人は少ないと思います。
それは、次また同じようなところで間違えるからです。うちの子そうでした。
やり直しって、実際にどのようにすれば効果が出てくるのでしょうか?
小学生の勉強で有効な「やり直し」の方法について調べました。
小学生の勉強でのやり直しとは?
小学生の勉強でのやり直しとは、間違えたところをもう一度考えて正しい答えを見つけるという作業です。
よく勘違いしているのが、間違えたところを答えを見て書き直し、「やり直した」と言う場合です。
これはやり直しではなく、書き直しです。ほとんどの場合、また同じところで間違えますし、正しいことが理解できていません。
やり直しとは、もう一度問題について考えてみることです。答えを写すことではありません。
やり直しの実際の方法
基本的なやり直しの方法は、自分が間違えたところをもう一度考え、答えを書くというやり方です。
小学校生活において、効果的なやり直し方が2つありますので、紹介します。
・テスト、プリントのやり直し
間違えたところのやり直しは、学校でするのが一番ですが、家に帰ってから勉強することもできます。
今回は、家でやり直しをする場合を説明します。
学校で使うドリルや問題集、教科書の問題のやり直し
子供達は、小学校で教科書や問題集を使って勉強しています。一番イメージしやすいのが算数です。
算数では、教科書に問題が載せてあります。不足する分をドリル集や問題集で補ってあります。学校から配られる計算ドリルなどです。
これらの問題は、勉強の基本となる大切な問題が多いですので、間違えたところはやり直すと、確実に成績はよくなります。
では、やり直しの手順です。
②家に帰って勉強するときに、〇がついている問題をやり直す。
③答え合わせをする。
④正解だったら、問題につけた〇に×を書く。(○は消さない)
間違いだったら、さらに番号に〇をつけ、◎にする。(間違えると増える)
単純なことなのですが、②が特に重要です。いきなり答えをみながらやり直すと、ただ答えを写しているだけになってしまいますから、問題だけ見てやり直すようにします。
普段から、間違えた問題に〇印をつけるようにしておくと、やり直しが習慣化できます。
④は、何度も間違えているところがよく分かるようになります。
テスト、プリントのやり直し
テスト、プリントのやり直しも、基本的には同じです。
②問題を読み、ノートにやり直して答えを書く。
③答え合わせをする。
④間違えた場合は、正しい答えを確認して、もう一度ノートにやり直す。
⑤テストやプリントは捨てずに、バインダーにとじていく。
テストやプリントの場合は、学校ですでにやり直している場合が多いです。正しい答えが書いてあります。
ですから、やり直しは、家に帰ってからノートにするほうがいいです。
ポイントは⑤です。特にテストは、勉強した内容がギュッとまとめられた1枚です。捨てずにファイルにとじておきます。
何度も後から復習に仕えるからです。
やり直しの重要なポイント
いろいろ場面でのやり直しの方法についてまとめてきましたが、どのやり直しの仕方にも共通する、とても重要なポイントがあります。
やり直しは1度で終わらない。2回3回とやり直すうちに、しっかりと理解できていくということです。
人間は忘れる生き物です。一度やり直したくらいで、100%覚えられるのなら、学校は成績優秀な子供であふれています。
そもそも、間違えたところは、分からなかったところですから。すぐにできるようになるとは思わないほうがいいです。
少し極端ですが、分かりやすいように鉄棒の例を出します。
逆上がりをする練習をしているとします。まだできない状態です。
先生から、「ここが違うんだ。こうするといいよ。」と、教えてもらったとします。自分のやり方の間違いを正してもらったということです。
しかし、だからといってすぐに逆上がりはできませんよね。
何が必要かというと、練習です。教えてもらったことを繰り返し練習していくのです。そうすれば逆上がりができるようになるかもしれません。
勉強も同じだと思います。
間違いが分かり、やり直しをした後は、それができるようになるために練習をしまければなりません。
この練習が、2回3回と繰り返し問題を解くことです。
最初から勉強ができる子なんていません。
やり直しをして、繰り返し練習していけば、必ず勉強が分かるようになります。


