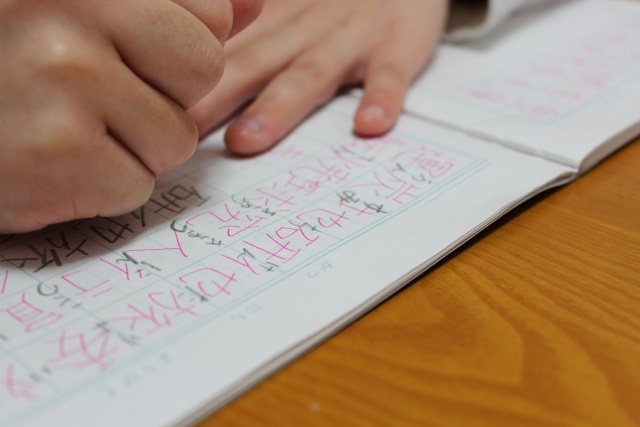論語とは、孔子の教えや弟子とのやり取りをまとめたものです。紀元前の出来事の話なのですが、現在も使われている言葉は多く、読んだ人の心に響きます。
今回は、論語の中から、わたしのおすすめの名言を紹介します。
論語の言葉
論語とは、孔子の言葉や弟子との会話をまとめたものです。詳しくはこちらの記事で「温故知新」とともに紹介しています。
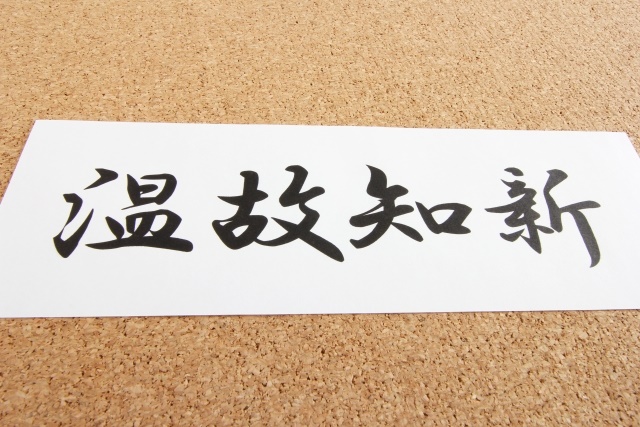
論語の中の言葉は、四字熟語やことわざ、慣用句として現在も多く使われています。それは、論語の言葉が心に響くからです。読む人が、論語の言葉に多くの共感を生むからです。
過ちて改めざる、これを即ち過ちという
「間違いは誰にでもあるもの。その間違いを犯しても、それを訂正し改めないこと。これが本当の過ちというのだ。」
心に響くというか痛みを感じる言葉です。ついつい間違っていると分かっているのに強情になったり、そのままにしてしまいます。わたしはよくあります。
間違いをそのままにしておくこと、これこそが間違いなんだと教えられているようです。
勉強でも当てはまりますよね。間違えているところがあったとして、そのままにしておくと、結局分からないままです。「テスト後はやり直しが大切なんだ。」と、よく言われました。
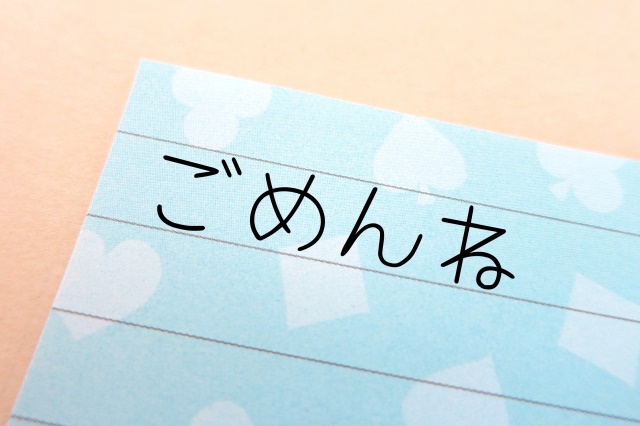
巧言令色すくなし仁
「言葉巧みに取り繕ったり、表面上のことばかり褒める人には、誠実な人はほとんどいない。」
この言葉を聞くと、以前家に来た訪問セールスの人を思い浮かべてしまいます。ソーラーパネルの販売だったと思います。
やたらとわたしの家のことを褒めてくれました。庭の様子や家のつくりなど、最高の誉め言葉をいただきました。
しかし、当時の家が借家であり、大家さんの許可なくソーラーパネルをつけることはできないということが分かると、言葉遣いも素っ気なくなり、さっさと去ってしまいました。
相手のことを本当に考えるのならば、ときには厳しいことも言わなければなりません。相手が嫌がる言葉も出てくるでしょう。それなのに、表面上取り繕う言葉だけの人信用できないということだと思います。
知らざるを知らずとなす、これ知るなり
「知らないことは知らないといえること、これが知るということだ。」
「過ちて改めざる」と似ているような気がします。はっきりと知らないようなことを知っていると言ったり、分かったようなふりをして学ぼうとしない。これは「知る」ということにはつながらないのだと教えてくれています。
分からないことは分からないとして、そこから知ろうとすることが大切だということだということですね。
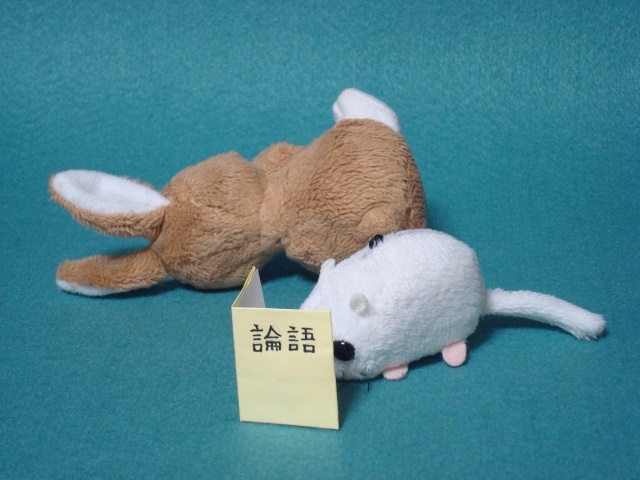
己の欲せざるところ、他人に施すことなかれ
「自分がしてほしくないことは、他人にもやってはいけない。」
子育ての場面でよく聞く言葉です。
「自分がされて嫌なことは、しちゃいけません!」
わたしもよく使っています。
自分がやってほしくないこと、それはつまり、誰にとって嫌なことなのです。その嫌なことを他の人にもやってはいけないと教えてくれています。
人と付き合う上では、当たり前のようなことですが、大切なことだと思います。
知る者は好む者にしかず、好む者は楽しむ者にしかず
知っているだけでは好きな人にはかなわない。好きなだけでは、楽しんでいる人にはかなわない。
ステキな言葉だと思います。珠玉の名言です。年齢が上がっていくにつれて、この言葉の意味を実感していくような気がします。
わたしは釣りが好きです。釣りを始めたての頃、釣り入門といった本ばかり読んでいました。読むといろいろな知識を得ることができ、なんだか釣りが上手になったような気がしていました。
しかし、実際には釣りが好きで毎日釣り場に通っている人には遠く及びませんでした。わずかなエサしか準備せず、釣りに行くということ自体を楽しんでいる人は、やはり達人級の腕前でした。
好きになること、楽しむことが上達の方法だと教えてくれているように思います。