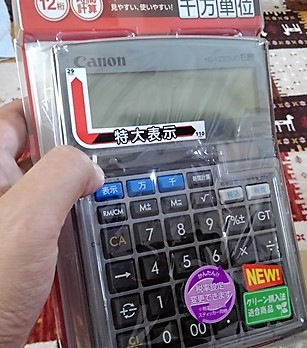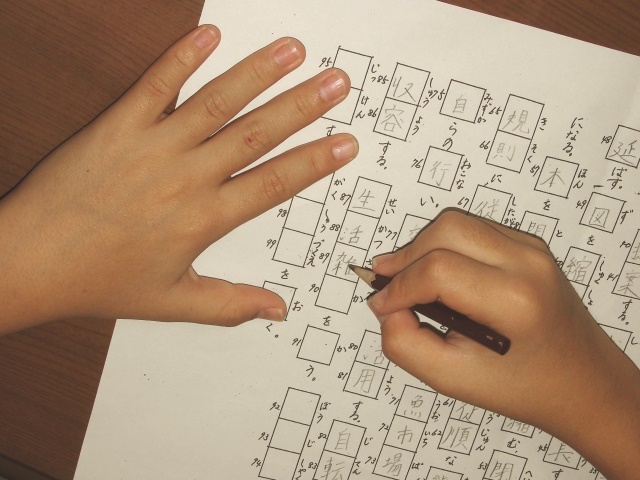
小学校の1学期が終わり、お子さんは夏休みに入ります。
学校からの通知表。いかがだったでしょうか?
昨年のうちの子の場合は、「復習すべきところがハッキリしている!」通知表でした。
具体的には国語と理科です。算数と社会は良かったです。きっと、本人も得意なんです。少し自信を持っていますからね。
この夏休み前と夏休み中の勉強で差がつきます。考えてみれば当たり前のことなんです。夏休みは30~40日あります。1日1時間勉強する子と、1日2時間勉強する子では、夏休みの終わりには30~40時間分の差が出来てしまいます。
ゆったりと過ごさせたい夏休みですが、この差が数年間続くと、ちょっとゾッとしますね。
さて、今回は、夏休み直前と夏休み中に行っておくと、グンと成績がアップする勉強方法、苦手が減る勉強方法を紹介します。
夏休み中の復習!1学期の復習はテストを使う!
まず、夏休み前や夏休み中に行う勉強は1学期の復習です。
学校から出される宿題も、実は復習する分しか出してありません。「勉強したことを、しっかりと理解してきてね!」ということなんですね。
そして、その勉強に最も効率的で効果が高いのは、これまで受けたテストを利用することなんです。捨ててませんよね?
テストには、その単元で勉強したことの大事なところが詰まっています。「ここだけは理解して欲しい!!」というところが問題にしてあるのです。どうでもいいところは、問題にされていません。
ですから、これまでのテストを全部引っぱり出して、もう一度徹底的に問題を解き直します。もちろん答えの部分はかくして解きます。
問題はテストを見ながら、答えはノートに書くようにします。
終わったら、すぐに答え合わせです。そして、間違えた問題はもう一度解くようにします。
これをやっておくだけで、1学期の復習はほとんど終了です。学力は格段に上がります。どこかの問題集や参考書を使うよりも何倍も効果がある勉強方です。
まだ「学期末まとめのテスト」が行われていないならチャンスです。まとめテスト用の勉強にもなりますよね。
ちなみに、2学期に入るとすぐテストがある小学校は少なくありません。この方法で復習しておけば、確実に2学期の最初のテストはいい結果がでます。
もちろん、夏休み終了前の1週間で、もう一度テストの復習をしておくことをおすすめします。
夏休みになって、この勉強を「自学」や「自主勉強」などの宿題で何度か繰り返しておけば、1学期に勉強したことはすっかり頭に入ってしまいます。お子さんの頭は優秀なのですよ。
まとめますね。夏休み直前や夏休み中のおススメ勉強方法は、1学期中に行われたテストのやり直しです。ノートに最低1回、1学期のテストをやり直すのです。
国語の勉強方は読む力アップを!
テストのやり直しをしながら、さらに学力アップを狙う方法もあります。
国語では、よくテストの裏の漢字問題の練習に時間を使っていませんか?
漢字の練習も大切なのですが、国語では読む力が最重要です。
テストの読み取り問題をしっかりと何度も解かせましょう。4月から7月まで勉強したことを、子供は何となく覚えています。
テストの読み取りの問題を見むことで、どんな勉強をしたのか思い出していきます。ですから、テストの表(おもて)面の読み取り問題を中心に、何度か勉強させると、読む力が確実にパワーアップします。
更に読む力をつけるには読書と読み取り問題集です。
例えばこちら。
またはこちら。
1日1回すらすら読解小5 小学国語 /数研出版/数研出版編集部
特に効果的なのは読み取り問題集です。1日1枚、5分程度で終わりますが、すごく読む力がついていきます。
読む力アップの勉強方法については、こちらでもまとめています。
>>国語の読解力をつける勉強方法
漢字はついでに2回くらい読み書きの練習をしましょう。テストの裏面には、漢字以外の言葉の勉強が問題として出されています。
例えば、主語と述語を探しましょうなどの問題です。国語辞典に出てくる順番の問題です。
返してもらったテストを捨てるなんてもったいない。1番の勉強の材料なのです。
算数の勉強方法はごちゃ混ぜ問題で理解力アップ!
多くの小学校のテストは、「単元別テスト」と呼ばれるテストです。小数の足し算の授業があれば、授業後には小数の足し算のテストがあるんです。
テスト用紙に「小数の足し算テスト」と書かれていたら、どんな問題でも、何となく足し算してれば間違えません。子供はそれを知っています。ほとんど足し算しか出ないのです。
ですから、1学期にテストが4枚実施されていたら、1枚目の問題を解いたら、次は3枚目の問題を解くなど、ごちゃ混ぜに問題を解かせましょう。
例えば、1学期に「小数のたし算・引き算」「三角形のかき方」「わり算」「長さ」の4つの勉強をしたとします。
ごちゃ混ぜとは、1問目に小数のたし算の問題を解き、2問目にわり算の問題、3問目に長さの問題、4問目に三角形のかき方の問題を解くということです。できればコピーして、1枚のテストにすれば最高です。
ごちゃ混ぜ問題を解くことで、頭の中が整理され、本当の算数の力がついてきます。これ、本当です。ぜひやってみてください。
学校によって扱われている「算数 1学期のまとめテスト」などもあります。たいてい1学期の終わりくらいにテストされます。
この1学期まとめテストが一番のごちゃ混ぜ問題です。1学期に勉強したことが、ほとんど詰め込まれています。点数が良くなくても大丈夫。このまとめテストをしっかりと勉強すれば、1学期に勉強したことがしっかりと復習できるのです。
すでに終わったテストのコピーなど、親の協力がかなり必要です。返されたテストのコピーをとり、白いB4の紙にごちゃまぜにして貼り付けて解かせましょう。算数の力がグンとついていく勉強方法です。
面倒な場合は、市販の教材もあります。学校のテストと同じようなテストがついているのがこちら。
ご購入の際には、お子さんの学年、教科書の出版社を確認して、合ったものを購入するようにしてください。全国の書店で購入できます。(もちろんネットでも)
理科の勉強方は深堀り(ふかほり)で興味アップ!
理科の復習のポイントは、興味を持ったことの深堀りです。どういうことかといいますと、『生き物のくらし方のテスト』があったとします。その中で、お子さんが昆虫に興味を持ったとします。その場合、テストのやり直しをしながら、興味を持った昆虫について調べさせるのです。
興味を持ったことを調べさせるには、図鑑が一番いいです。最近の小学生向け図鑑はすごく考えて作られています。お子さんが興味をもっと持てるように作られているのです。図鑑の値段は高いので、本のリサイクルショップなどで安く手に入りますよ。
ついでに夏休みの自由研究にしてしまうこともできます。お子さんの興味も満たされ、自由研究まで終わらせることができ一石二鳥です。
子供は、好きなことは喜んでやります。それで褒められれば、さらに調子にのります。
興味をもったこと、自分で調べたっこと、自分だけが知っていることは、忘れません。
社会の勉強方は図でまとめ力アップ!
理科も社会も、国語や算数に比べると、テストの枚数自体が少ないです。2~4枚です。
復習はあっという間に終わります。
社会で大切なのは、仕組みの理解です
例えば、小学校4年生で、水の勉強をします。わたしたちの家に水が届くまで、どのような仕組みで水が届くのか勉強するのです。
ついつい貯水槽やろ過などの言葉の意味を中心に勉強してしまいがちです。しかし、社会のテストでは、ほとんどが図や絵、写真で問題がつくられています。これは、社会は知識を覚える勉強ではなく、仕組み理解する勉強だということです。
ですから、社会では、テストにのっている水が届く仕組みの図などをノートに写して、その仕組みを理解する勉強を大切にします。確実に社会がおもしろくなります。
よく分からない場合は、社会のテストの絵や図をノートに写して復習するとよいということです。
ですが、せっかくの夏休みなので、じっくり勉強させたいという親心もあるでしょう。そんな場合は、算数で紹介した「教科書ワーク」シリーズが1番おすすめです。もしくは「ポピー」。
2つとも学校の教科書に合わせてつくられているので、小学生には勉強しやすいのです。気になる方は、ポピーには無料のお試しがありますので、一度お試しください。
![]()
1学期の勉強は、1学期のうちに理解しておきましょう。
楽しい夏休みを迎え、充実した夏休みが過ごせるといいですね。
何かお問い合わせやご感想がありましたら、遠慮なくどうぞ!